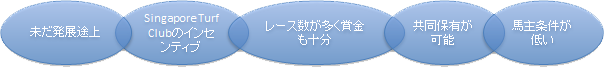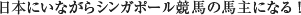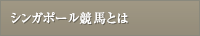馬主であれば誰でも、自分の馬の成長と勝利を望みます。しかしアジアの中でもトップレベルとなった日本競馬ではなかなか簡単なことではありません。では、日本の調教を受けた競走馬が、競馬レベルが発展途上の地域で出走したとしたら、いかがでしょうか?輝かしい成績や賞金も狙える競争馬になる、そしてその馬主になることも夢ではなくなります。未だ発展途上段階でありながら人気があり、馬主になる為の資産条件がないシンガポール競馬であれば、名馬主となる可能性は更に高くなるでしょう。日本にいながら、馬主条件も低く伸びしろのあるシンガポールで、馬主という投資にチャレンジしてみませんか?現地ではシンガポールでベスト3に入る厩舎がサポートいたします。更に、日本の調教技術を現地でも加えるオプションもご用意しております(要相談)。


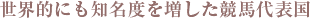
- 日本はアジアでは最も競馬の盛んな国ですが、世界的に見ても大きな売上を上げています。世界最大のサラブレット生産国はアメリカですが、日本もオーストラリアやイギリスと並んで世界的な良馬生産地といわれています。
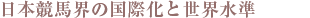
- というのも、日本は国際招待試合(ジャパンカップ・重賞GⅠ)開催や国際試合への参加など、海外競走馬と競うことで世界標準の「強い馬づくり」への意識を高く持てる環境基盤があります。更に、日本人の性格らしく、馬の特徴を見極めて伸ばしながらじっくり育てる傾向も相まって、日本の競走馬・調教技術は独自のスタイルを確立しつつあります。
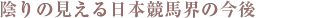
- しかし、最近の日本のレジャービジネス全般にあてはまりますが、長引く不況の影響と、レジャーの多様化がますます進み、市場規模のマイナス成長が続いています。特に、レジャーの中でも不況に強いといわれ、バブル崩壊後も大きな打撃を受けなかった“ギャンブル型レジャー業界”(競輪・競馬などの公営5競技やパチンコ、宝くじなど)ですが、公営5競技はその後毎年のように売上額が減少傾向にあることをはじめ、ここ数年特に不振にあえいでいます。
中央競馬は武豊やナリタブライアンなどの登場に因って平成8・9年は持ち直したものの、その後はやはり減少傾向にあることは事実です。平成24年は前年比プラスに転じましたが、平成26年以降の消費税増税の影響は免れられないでしょう。
地方競馬はさらに厳しく、平成3年には9,820億円だった売上が、平成24年には3,320億円と66%も落ちています。平成12年にはすべての主催者(施行者)で赤字を計上し、九州の中津競馬や新潟県競馬など、施行者の撤退が相次いでいます。
日本競馬の売り上げグラフ


- 歴史と現在
- シンガポール競馬は、日本と歴史の長さはさほど変わらないものの、調教技術は高くありません。また三冠レースをはじめとして、レースはローカルG1が中心であり、アジアで日本に次ぐ競馬が盛んな国である香港と同様に未だパートⅡ区となっています。
(※日本も2007年に国際セリ名簿基準委員会によってパートⅠ国認定されるまではJRAもローカルG1でした) - シンガポールのこれから
- アジア圏はこれからのビジネス市場として世界各国が注目している地域であり、競馬業界でも今後、ますます海外馬の参入が予想できます。かつての日本のように、海外競走馬によるレベルアップが期待できますが、まだその動きは小さなものです。シンガポールでは自国の競馬業界の発展に力入れています。シンガポール・ターフ・クラブのインセンティヴや賞金額の増加により、シンガポール市民以外の馬主への門戸が開かれ、現在では競走馬保有の6割がローカル・4割が海外オーナーになるなどグローバル化が進んでいます。結果、競走馬の数は2007年の2倍の1,400頭までになり、市場は世界中から常連客を誘致するまでになりました。年当りの賞金総額は62,000,000ドル(約63億円)にも昇るうえに、馬主条件も低く、保有権も1%から100%まで様々であることも、プラスに働いています。年1000回近くのレースに参加できることを考えても、厩舎スペース当りの賞金総額はとてつもなく大きくなります。まだシンガポールの競馬レベルが低いうちに好成績を残し、名馬となることで種馬としての価値も上がります。自分の競争馬が今後のシンガポール競馬の発展の礎となった名馬として、シンガポール競馬の歴史に名を連ねることになるかも知れません。